北守将軍と三人兄弟の医者
一、三人兄弟の医者
むかしラユーという首都に、兄弟三人の医者がいた。いちばん上のリンパーは、普通の人の医者だった。その弟のリンプーは、馬や羊の医者だった。いちばん末のリンポーは、草だの木だのの医者だった。そして兄弟三人は、町のいちばん南にあたる、黄いろな崖のとっぱなへ、青い瓦の病院を、三つならべて建てていて、てんでに白や朱の旗を、風にぱたぱた云わせていた。
坂のふもとで見ていると、漆にかぶれた坊さんや、少しびっこをひく馬や、萎れかかった牡丹の鉢を、車につけて引く園丁や、いんこを入れた鳥籠や、次から次とのぼって行って、さて坂上に行き着くと、病気の人は、左のリンパー先生へ、馬や羊や鳥類は、中のリンプー先生へ、草木をもった人たちは、右のリンポー先生へ、三つにわかれてはいるのだった。
さて三人は三人とも、実に医術もよくできて、また仁心も相当あって、たしかにもはや名医の類であったのだが、まだいい機会がなかったために別に位もなかったし、遠くへ名前も聞えなかった。ところがとうとうある日のこと、ふしぎなことが起ってきた。
二、北守将軍ソンバーユー
ある日のちょうど日の出ごろ、ラユーの町の人たちは、はるかな北の野原の方で、鳥か何かがたくさん群れて、声をそろえて鳴くような、おかしな音を、ときどき聴いた。はじめは誰も気にかけず、店を掃いたりしていたが、朝めしすこしすぎたころ、だんだんそれが近づいて、みんな立派なチャルメラや、ラッパの音だとわかってくると、町じゅうにわかにざわざわした。その間にはぱたぱたいう、太鼓の類の音もする。もう商人も職人も、仕事がすこしも手につかない。門を守った兵隊たちは、まず門をみなしっかりとざし、町をめぐった壁の上には、見張りの者をならべて置いて、それからお宮へ知らせを出した。
そしてその日の午ちかく、ひづめの音や鎧の気配、また号令の声もして、向うはすっかり、この町を、囲んでしまった模様であった。
番兵たちや、あらゆる町の人たちが、まるでどきどきやりながら、矢を射る孔からのぞいて見た。壁の外から北の方、まるで雲霞の軍勢だ。ひらひらひかる三角旗や、ほこがさながら林のようだ。ことになんとも奇体なことは、兵隊たちが、みな灰いろでぼさぼさして、なんだかけむりのようなのだ。するどい眼をして、ひげが二いろまっ白な、せなかのまがった大将が、尻尾が箒のかたちになって、うしろにぴんとのびている白馬に乗って先頭に立ち、大きな剣を空にあげ、声高々と歌っている。
「北守将軍ソンバーユーは
いま塞外の砂漠から
やっとのことで戻ってきた。
勇ましい凱旋だと云いたいが
実はすっかり参って来たのだ
とにかくあすこは寒い処さ。
三十年という黄いろなむかし
おれは十万の軍勢をひきい
この門をくぐって威張って行った。
それからどうだもう見るものは空ばかり
風は乾いて砂を吹き
雁さえ干せてたびたび落ちた
おれはその間馬でかけ通し
馬がつかれてたびたびペタンと座り
涙をためてはじっと遠くの砂を見た。
その度ごとにおれは鎧のかくしから
塩をすこうし取り出して
馬に嘗めさせては元気をつけた。
その馬も今では三十五歳
五里かけるにも四時間かかる。
それからおれはもう七十だ。
とても帰れまいと思っていたが
ありがたや敵が残らず脚気で死んだ
今年の夏はへんに湿気が多かったでな。
それに脚気の原因が
あんまりこっちを追いかけて
砂を走ったためなんだ
そうしてみればどうだやっぱり凱旋だろう。
殊にも一つほめられていいことは
十万人もでかけたものが
九万人まで戻って来た。
死だやつらは気の毒だが
三十年の間には
たとえいくさに行かなくたって
一割ぐらいは死ぬんじゃないか。
そこでラユーのむかしのともよ
またこどもらよきょうだいよ
北守将軍ソンバーユーと
その軍勢が帰ったのだ
門をあけてもいいではないか。」
さあ城壁のこっちでは、湧きたつような騒動だ。うれしまぎれに泣くものや、両手をあげて走るもの、じぶんで門をあけようとして、番兵たちに叱られるもの、もちろん王のお宮へは使が急いで走って行き、城門の扉はぴしゃんと開いた。おもての方の兵隊たちも、もううれしくて、馬にすがって泣いている。
顔から肩から灰いろの、北守将軍ソンバーユーは、わざとくしゃくしゃ顔をしかめ、しずかに馬のたづなをとって、まっすぐを向いて先登に立ち、それからラッパや太鼓の類、三角ばたのついた槍、まっ青に錆びた銅のほこ、それから白い矢をしょった、兵隊たちが入ってくる。馬は太鼓に歩調を合せ、殊にもさきのソン将軍の白馬は、歩くたんびに膝がぎちぎち音がして、ちょうどひょうしをとるようだ。兵隊たちは軍歌をうたう。
「みそかの晩とついたちは
砂漠に黒い月が立つ。
西と南の風の夜は
月は冬でもまっ赤だよ。
雁が高みを飛ぶときは
敵が遠くへ遁げるのだ。
追おうと馬にまたがれば
にわかに雪がどしゃぶりだ。」
兵隊たちは進んで行った。九万の兵というものはただ見ただけでもぐったりする。
「雪の降る日はひるまでも
そらはいちめんまっくらで
わずかに雁の行くみちが
ぼんやり白く見えるのだ。
砂がこごえて飛んできて
枯れたよもぎをひっこぬく。
抜けたよもぎは次次と
都の方へ飛んで行く。」
みんなは、みちの両側に、垣をきずいて、ぞろっとならび、泪を流してこれを見た。
かくて、バーユー将軍が、三町ばかり進んで行って、町の広場についたとき、向うのお宮の方角から、黄いろな旗がひらひらして、誰かこっちへやってくる。これはたしかに知らせが行って、王から迎いが来たのである。
ソン将軍は馬をとめ、ひたいに高く手をかざし、よくよくそれを見きわめて、それから俄かに一礼し、急いで、馬を降りようとした。ところが馬を降りれない、もう将軍の両足は、しっかり馬の鞍につき、鞍はこんどは、がっしりと馬の背中にくっついて、もうどうしてもはなれない。さすが豪気の将軍も、すっかりあわてて赤くなり、口をびくびく横に曲げ、一生けん命、はね下りようとするのだが、どうにもからだがうごかなかった。ああこれこそじつに将軍が、三十年も、国境の空気の乾いた砂漠のなかで、重いつとめを肩に負い、一度も馬を下りないために、馬とひとつになったのだ。おまけに砂漠のまん中で、どこにも草の生えるところがなかったために、多分はそれが将軍の顔を見付けて生えたのだろう。灰いろをしたふしぎなものがもう将軍の顔や手や、まるでいちめん生えていた。兵隊たちにも生えていた。そのうち使いの大臣は、だんだん近くやって来て、もうまっさきの大きな槍や、旗のしるしも見えて来た。
将軍、馬を下りなさい。王様からのお迎いです。将軍、馬を下りなさい。向うの列で誰か云う。将軍はまた手をばたばたしたが、やっぱりからだがはなれない。
ところが迎いの大臣は、鮒よりひどい近眼だった。わざと馬から下りないで、両手を振って、みんなに何か命令してると考えた。
「謀叛だな。よし。引き上げろ。」そう大臣はみんなに云った。そこで大臣一行は、くるっと馬を立て直し、黄いろな塵をあげながら、一目散に戻って行く。ソン将軍はこれを見て肩をすぼめてため息をつき、しばらくぼんやりしていたが、俄かにうしろを振り向いて、軍師の長を呼び寄せた。
「おまえはすぐに鎧を脱いで、おれの刀と弓をもち、早くお宮へ行ってくれ。それから誰かにこう云うのだ。北守将軍ソンバーユーは、あの国境の砂漠の上で、三十年のひるも夜も、馬から下りるひまがなく、とうとうからだが鞍につき、そのまた鞍が馬について、どうにもお前へ出られません。これからお医者に行きまして、やがて参内いたします。こうていねいに云ってくれ。」
軍師の長はうなずいて、すばやく鎧と兜を脱ぎ、ソン将軍の刀をもって、一目散にかけて行く。ソン将軍はみんなに云った。
「全軍しずかに馬をおり、兜をぬいで地に座れ。ソン大将はただ今から、ちょっとお医者へ行ってくる。そのうち音をたてないで、じいっとやすんでいてくれい。わかったか。」
「わかりました。将軍」兵隊共は声をそろえて一度に叫ぶ。将軍はそれを手で制し、急いで馬に鞭うった。たびたびぺたんと砂漠に寝た、この有名な白馬は、ここで最後の力を出し、がたがたがたがた鳴りながら、風より早くかけ出した。さて将軍は十町ばかり、夢中で馬を走らせて、大きな坂の下に来た。それから俄かにこう云った。
「上手な医者はいったい誰だ。」
一人の大工が返事した。
「それはリンパー先生です。」
「そのリンパーはどこに居る。」
「すぐこの坂のま上です。あの三つある旗のうち、一番左でございます。」
「よろしい、しゅう。」と将軍は、例の白馬に一鞭くれて、一気に坂をかけあがる。大工はあとでぶつぶつ云った。
「何だ、あいつは野蛮なやつだ。ひとからものを教わって、よろしい、しゅう とはいったいなんだ。」
ところがバーユー将軍は、そんなことには構わない。そこらをうろうろあるいている、病人たちをはね越えて、門の前まで上っていた。なるほど門のはしらには、小医リンパー先生と、金看板がかけてある。
三、リンパー先生
さてソンバーユー将軍は、いまやリンパー先生の、大玄関を乗り切って、どしどし廊下へ入って行く。さすがはリンパー病院だ、どの天井も室の扉も、高さが二丈ぐらいある。
「医者はどこかね。診てもらいたい。」ソン将軍は号令した。
「あなたは一体何ですか。馬のまんまで入るとは、あんまり乱暴すぎましょう。」萌黄の長い服を着て、頭を剃った一人の弟子が、馬のくつわをつかまえた。
「おまえが医者のリンパーか、早くわが輩の病気を診ろ。」
「いいえ、リンパー先生は、向うの室に居られます。けれどもご用がおありなら、馬から下りていただきたい。」
「いいや、そいつができんのじゃ。馬からすぐに下りれたら、今ごろはもう王様の、前へ行ってた筈なんじゃ。」
「ははあ、馬から降りられない。そいつは脚の硬直だ。そんならいいです。おいでなさい。」
弟子は向うの扉をあけた。ソン将軍はぱかぱかと馬を鳴らしてはいって行った。中には人がいっぱいで、そのまん中に先生らしい、小さな人が床几に座り、しきりに一人の眼を診ている。
「ひとつこっちをたのむのじゃ。馬から降りられないでのう。」そう将軍はやさしく云った。ところがリンパー先生は、見向きもしないし動きもしない。やっぱりじっと眼を見ている。
「おい、きみ、早くこっちを見んか。」将軍が怒鳴り出したので、病人たちはびくっとした。ところが弟子がしずかに云った。
「診るには番がありますからな。あなたは九十六番で、いまは六人目ですから、もう九十人お待ちなさい。」
「黙れ、きさまは我輩に、七十二人待てっと云うか。おれを誰だと考える。北守将軍ソンバーユーだ。九万人もの兵隊を、町の広場に待たせてある。おれが一人を待つことは七万二千の兵隊が、向うの方で待つことだ。すぐ見ないならけちらすぞ。」将軍はもう鞭をあげ馬は一いきはねあがり、病人たちは泣きだした。ところがリンパー先生は、やっぱりびくともしていない、てんでこっちを見もしない。その先生の右手から、黄の綾を着た娘が立って、花瓶にさした何かの花を、一枝とって水につけ、やさしく馬につきつけた。馬はぱくっとそれを噛み、大きな息を一つして、ぺたんと四つ脚を折り、今度はごうごういびきをかいて、首を落してねむってしまう。ソン将軍はまごついた。
「あ、馬のやつ、又参ったな。困った。困った。困った。」と云って、急いで鎧のかくしから、塩の袋をとりだして、馬に喰べさせようとする。
「おい、起きんかい。あんまり情けないやつだ。あんなにひどく難儀して、やっと都に帰って来ると、すぐ気がゆるんで死ぬなんて、ぜんたいどういう考なのか。こら、起きんかい。起きんかい。しっ、ふう、どう、おい、この塩を、ほんの一口たべんかい。」それでも馬は、やっぱりぐうぐうねむっている。ソン将軍はとうとう泣いた。
「おい、きみ、わしはとにかくに、馬だけどうかみてくれたまえ。こいつは北の国境で、三十年もはたらいたのだ。」
むすめはだまって笑っていたが、このときリンパー先生が、いきなりこっちを振り向いて、まるで将軍の胸底から、馬の頭も見徹すような、するどい眼をしてしずかに云った。
「馬はまもなく治ります。あなたの病気をしらべるために、馬を座らせただけです。あなたはそれで向うの方で、何か病気をしましたか。」
「いいや、病気はしなかった。病気は別にしなかったが、狐のために欺されて、どうもときどき困ったじゃ。」
「それは、どういう風ですか。」
「向うの狐はいかんのじゃ。十万近い軍勢を、ただ一ぺんに欺すんじゃ。夜に沢山火をともしたり、昼間いきなり砂漠の上に、大きな海をこしらえて、城や何かも出したりする。全くたちが悪いんじゃ。」
「それを狐がしますのですか。」
「狐とそれから、砂鶻じゃね、砂鶻というて鳥なんじゃ。こいつは人の居らないときは、高い処を飛んでいて、誰かを見ると試しに来る。馬のしっぽを抜いたりね。目をねらったりするもんで、こいつがでたらもう馬は、がたがたふるえてようあるかんね。」
「そんなら一ぺん欺されると、何日ぐらいでよくなりますか。」
「まあ四日じゃね。五日のときもあるようじゃ。」
「それであなたは今までに、何べんぐらい欺されました?」
「ごく少くて十ぺんじゃろう。」
「それではお尋ねいたします。百と百とを加えると答はいくらになりますか。」
「百八十じゃ。」
「それでは二百と二百では。」
「さよう、三百六十だろう。」
「そんならも一つ伺いますが、十の二倍は何ほどですか。」
「それはもちろん十八じゃ。」
「なるほど、すっかりわかりました。あなたは今でもまだ少し、砂漠のためにつかれています。つまり十パーセントです。それではなおしてあげましょう。」
パー先生は両手をふって、弟子にしたくを云い付けた。弟子は大きな銅鉢に、何かの薬をいっぱい盛って、布巾を添えて持って来た。ソン将軍は両手を出して鉢をきちんと受けとった。パー先生は片袖まくり、布巾に薬をいっぱいひたし、かぶとの上からざぶざぶかけて、両手でそれをゆすぶると、兜はすぐにすぱりととれた。弟子がも一人、もひとつ別の銅鉢へ、別の薬をもってきた。そこでリンパー先生は、別の薬でじゃぶじゃぶ洗う。雫はまるでまっ黒だ。ソン将軍は心配そうに、うつむいたまま訊いている。
「どうかね、馬は大丈夫かね。」「もうじきです。」とパー先生は、つづけてじゃぶじゃぶ洗っている。雫がだんだん茶いろになって、それからうすい黄いろになった。それからとうとうもう色もなく、ソン将軍の白髪は、熊より白く輝いた。そこでリンパー先生は、布巾を捨てて両手を洗い、弟子は頭と顔を拭く。将軍はぶるっと身ぶるいして、馬にきちんと起きあがる。
「どうです、せいせいしたでしょう。ところで百と百とをたすと、答はいくらになりますか。」
「もちろんそれは二百だろう。」
「そんなら二百と二百とたせば。」
「さよう、四百にちがいない。」
「十の二倍はどれだけですか。」
「それはもちろん二十じゃな。」さっきのことは忘れた風で、ソン将軍はけろりと云う。
「すっかりおなおりなりました。つまり頭の目がふさがって、一割いけなかったのですな。」
「いやいや、わしは勘定などの、十や二十はどうでもいいんじゃ。それは算師がやるでのう。わしは早速この馬と、わしをはなしてもらいたいんじゃ。」
「なるほどそれはあなたの足を、あなたの服と引きはなすのは、すぐ私に出来るです。いやもう離れている筈です。けれども、ずぼんが鞍につき、鞍がまた馬についたのを、はなすというのは別ですな。それはとなりで、私の弟がやっていますから、そっちへおいでいただきます。それにいったいこの馬もひどい病気にかかっています。」
「そんならわしの顔から生えた、このもじゃもじゃはどうじゃろう。」
「そちらもやっぱり向うです。とにかくひとつとなりの方へ、弟子をお供に出しましょう。」
「それではそっちへ行くとしよう。ではさようなら。」さっきの白いきものをつけた、むすめが馬の右耳に、息を一つ吹き込んだ。馬はがばっとはねあがり、ソン将軍は俄かに背が高くなる。将軍は馬のたづなをとり、弟子とならんで室を出る。それから庭をよこぎって厚い土塀の前に来た。小さな潜りがあいている。
「いま裏門をあけさせましょう。」助手は潜りを入って行く。
「いいや、それには及ばない。わたしの馬はこれぐらい、まるで何とも思ってやしない。」
将軍は馬にむちをやる。
ぎっ、ばっ、ふう。馬は土塀をはね越えて、となりのリンプー先生の、けしのはたけをめちゃくちゃに、踏みつけながら立っていた。
四、馬医リンプー先生
ソン将軍が、お医者の弟子と、けしの畑をふみつけて向うの方へ歩いて行くと、もうあっちからもこっちからも、ぶるるるふうというような、馬の仲間の声がする。そして二人が正面の、巨きな棟にはいって行くと、もう四方から馬どもが、二十疋もかけて来て、蹄をことこと鳴らしたり、頭をぶらぶらしたりして、将軍の馬に挨拶する。
向うでリンプー先生は、首のまがった茶いろの馬に、白い薬を塗っている。さっきの弟子が進んで行って、ちょっと何かをささやくと、馬医のリンプー先生は、わらってこっちをふりむいた。巨きな鉄の胸甲を、がっしりはめていることは、ちょうどやっぱり鎧のようだ。馬にけられぬためらしい。将軍はすぐその前へ、じぶんの馬を乗りつけた。
「あなたがリンプー先生か。わしは将軍ソンバーユーじゃ。何分ひとつたのみたい。」
「いや、その由を伺いました。あなたのお馬はたしか三十九ぐらいですな。」
「四捨五入して、そうじゃ、やっぱり三十九じゃな。」
「ははあ、ただいま手術いたします。あなたは馬の上に居て、すこし煙いかしれません。それをご承知くださいますか。」
「煙い? なんのどうして煙ぐらい、砂漠で風の吹くときは、一分間に四十五以上、馬を跳躍させるんじゃ。それを三つも、やすんだら、もう頭まで埋まるんじゃ。」
「ははあ、それではやりましょう。おい、フーシュ。」プー先生は弟子を呼ぶ。弟子はおじぎを一つして、小さな壺をもって来た。プー先生は蓋をとり、何か茶いろな薬を出して、馬の眼に塗りつけた。それから「フーシュ」とまた呼んだ。弟子はおじぎを一つして、となりの室へ入って行って、しばらくごとごとしていたが、まもなく赤い小さな餅を、皿にのっけて帰って来た。先生はそれをつまみあげ、しばらく指ではさんだり、匂をかいだりしていたが、何か決心したらしく、馬にぱくりと喰べさせた。ソン将軍は、その白馬の上に居て、待ちくたびれてあくびをした。すると俄かに白馬は、がたがたがたがたふるえ出しそれからからだ一面に、あせとけむりを噴き出した。プー先生はこわそうに、遠くへ行ってながめている。がたがたがたがた鳴りながら、馬はけむりをつづけて噴いた。そのまた煙が無暗に辛い。ソン将軍も、はじめは我慢していたが、とうとう両手を眼にあてて、ごほんごほんとせきをした。そのうちだんだんけむりは消えてこんどは、汗が滝よりひどくながれだす。プー先生は近くへよって、両手をちょっと鞍にあて、二っつばかりゆすぶった。
たちまち鞍はすぱりとはなれ、はずみを食った将軍は、床にすとんと落された。ところがさすが将軍だ。いつかきちんと立っている。おまけに鞍と将軍も、もうすっかりとはなれていて、将軍はまがった両足を、両手でぱしゃぱしゃ叩いたし、馬は俄かに荷がなくなって、さも見当がつかないらしく、せなかをゆらゆらゆすぶった。するとリンプー先生はこんどは馬のほうきのようなしっぽを持って、いきなりぐっと引っ張った。すると何やらまっ白な、尾の形した塊が、ごとりと床にころがり落ちた。馬はいかにも軽そうに、いまは全く毛だけになったしっぽを、ふさふさ振っている。弟子が三人集って、馬のからだをすっかりふいた。
「もういいだろう。歩いてごらん。」
馬はしずかに歩きだす。あんなにぎちぎち軋んだ膝がいまではすっかり鳴らなくなった。プー先生は手をあげて、馬をこっちへ呼び戻し、おじぎを一つ将軍にした。
「いや謝しますじゃ。それではこれで。」将軍は、急いで馬に鞍を置き、ひらりとそれにまたがれば、そこらあたりの病気の馬は、ひんひん別れの挨拶をする。ソン将軍は室を出て塀をひらりと飛び越えて、となりのリンポー先生の、菊のはたけに飛び込んだ。
五、リンポー先生
さてもリンポー先生の、草木を治すその室は、林のようなものだった。あらゆる種類の木や花が、そこらいっぱいならべてあって、どれにもみんな金だの銀の、巨きな札がついている。そこを、バーユー将軍は、馬から下りて、ゆっくりと、ポー先生の前へ行く。さっきの弟子がさきまわりして、すっかり談していたらしく、ポー先生は薬の函と大きな赤い団扇をもって、ごくうやうやしく待っていた。ソン将軍は手をあげて、
「これじゃ。」と顔を指さした。ポー先生は黄いろな粉を、薬函から取り出して、ソン将軍の顔から肩へ、もういっぱいにふりかけて、それから例のうちわをもって、ばたばたばたばた扇ぎ出す。するとたちまち、将軍の、顔じゅうの毛はまっ赤に変り、みんなふわふわ飛び出して、見ているうちに将軍は、すっかり顔がつるつるなった。じつにこのとき将軍は、三十年ぶりにっこりした。
「それではこれで行きますじゃ。からだもかるくなったでのう。」もう将軍はうれしくて、はやてのように室を出て、おもての馬に飛び乗れば、馬はたちまち病院の、巨きな門を外に出た。あとから弟子が六人で、兵隊たちの顔から生えた灰いろの毛をとるために、薬の袋とうちわをもって、ソン将軍を追いかけた。
六、北守将軍仙人となる
さてソンバーユー将軍は、ポー先生の玄関を、光のように飛び出して、となりのリンプー病院を、はやてのごとく通り過ぎ、次のリンパー病院を、斜めに見ながらもう一散に、さっきの坂をかけ下りる。馬は五倍も速いので、もう向うには兵隊たちの、やすんでいるのが見えてきた。兵隊たちは心配そうにこっちの方を見ていたのだが、思わず歓呼の声をあげ、みんな一緒に立ちあがる。そのときお宮の方からはさっきの使いの軍師の長が一目散にかけて来た。
「ああ、王様は、すっかりおわかりなりました。あなたのことをおききになって、おん涙さえ浮べられ、お出でをお待ちでございます。」
そこへさっきの弟子たちが、薬をもってやってきた。兵隊たちはよろこんで、粉をふってはばたばた扇ぐ。そこで九万の軍隊は、もう輪廓もはっきりなった。
将軍は高く号令した。
「馬にまたがり、気をつけいっ。」
みんなが馬にまたがれば、まもなくそこらはしんとして、たった二疋の遅れた馬が、鼻をぶるっと鳴らしただけだ。
「前へ進めっ。」太鼓も銅鑼も鳴り出して、軍は粛々行進した。
やがて九万の兵隊は、お宮の前の一里の庭に縦横ちょうど三百人、四角な陣をこしらえた。
ソン将軍は馬を降り、しずかに壇をのぼって行って床に額をすりつけた。王はしずかに斯ういった。
「じつに永らくご苦労だった。これからはもうここに居て、大将たちの大将として、なお忠勤をはげんでくれ。」
北守将軍ソンバーユーは涙を垂れてお答えした。
「おことばまことに畏くて、何とお答えいたしていいか、とみに言葉も出でませぬ。とは云えいまや私は、生きた骨ともいうような、役に立たずでございます。砂漠の中に居ました間、どこから敵が見ているか、あなどられまいと考えて、いつでもりんと胸を張り、眼を見開いて居りましたのが、いま王様のお前に出て、おほめの詞をいただきますと、俄かに眼さえ見えぬよう。背骨も曲ってしまいます。何卒これでお暇を願い、郷里に帰りとうございます。」
「それでは誰かおまえの代り、大将五人の名を挙げよ。」
そこでバーユー将軍は、大将四人の名をあげた。そして残りの一人の代り、リン兄弟の三人を国のお医者におねがいした。王は早速許されたので、その場でバーユー将軍は、鎧もぬげば兜もぬいで、かさかさ薄い麻を着た。そしてじぶんの生れた村のス山の麓へ帰って行って、粟をすこうし播いたりした。それから粟の間引きもやった。けれどもそのうち将軍は、だんだんものを食わなくなってせっかくじぶんで播いたりした、粟も一口たべただけ、水をがぶがぶ呑んでいた。ところが秋の終りになると、水もさっぱり呑まなくなって、ときどき空を見上げては何かしゃっくりするようなきたいな形をたびたびした。
そのうちいつか将軍は、どこにも形が見えなくなった。そこでみんなは将軍さまは、もう仙人になったと云って、ス山の山のいただきへ小さなお堂をこしらえて、あの白馬は神馬に祭り、あかしや粟をささげたり、麻ののぼりをたてたりした。
けれどもこのとき国手になった例のリンパー先生は、会う人ごとに斯ういった。
「どうして、バーユー将軍が、雲だけ食った筈はない。おれはバーユー将軍の、からだをよくみて知っている。肺と胃の腑は同じでない。きっとどこかの林の中に、お骨があるにちがいない。」なるほどそうかもしれないと思った人もたくさんあった。
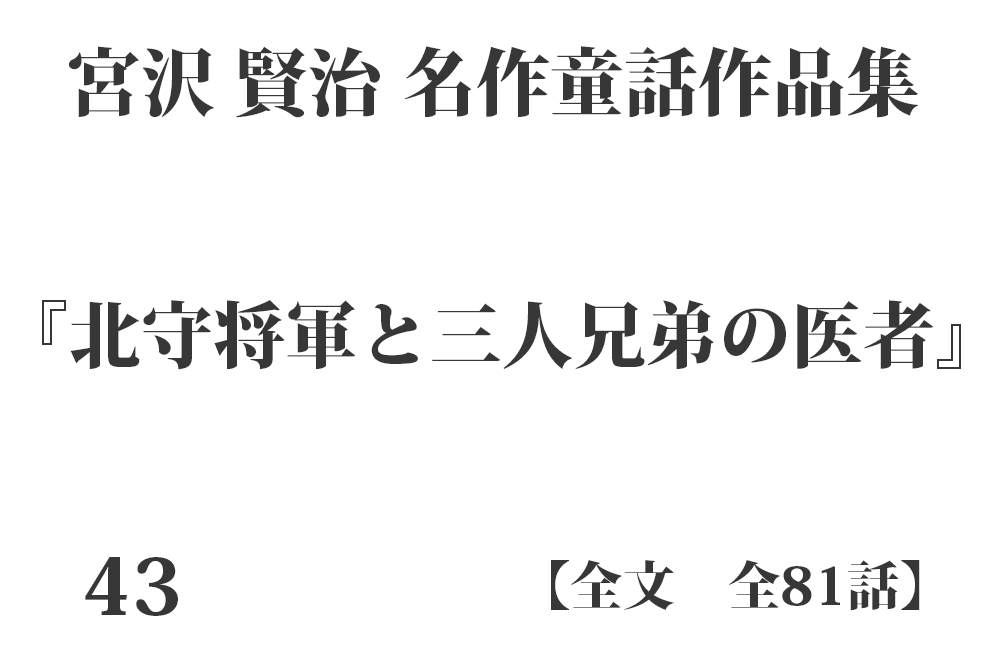
コメント